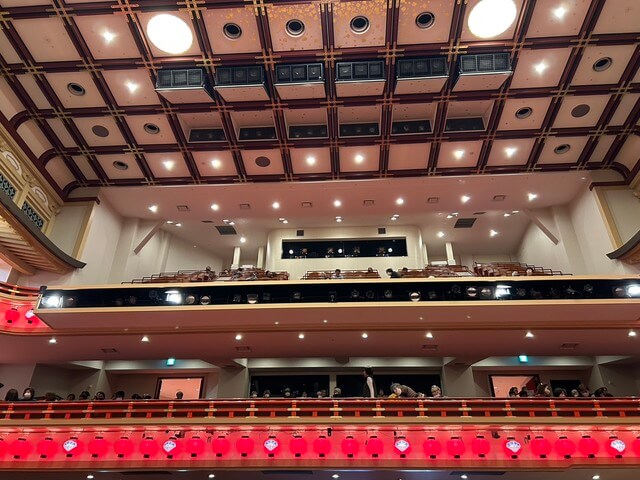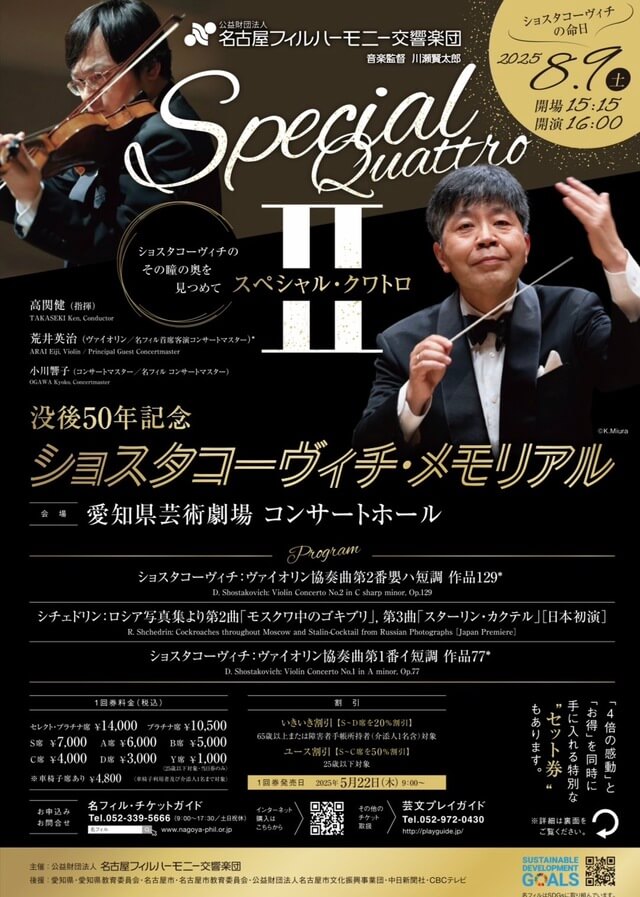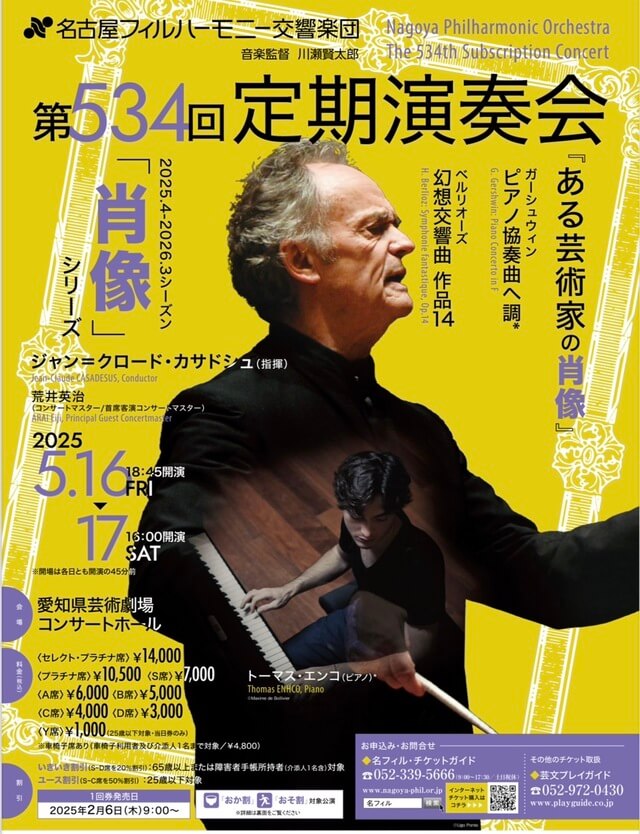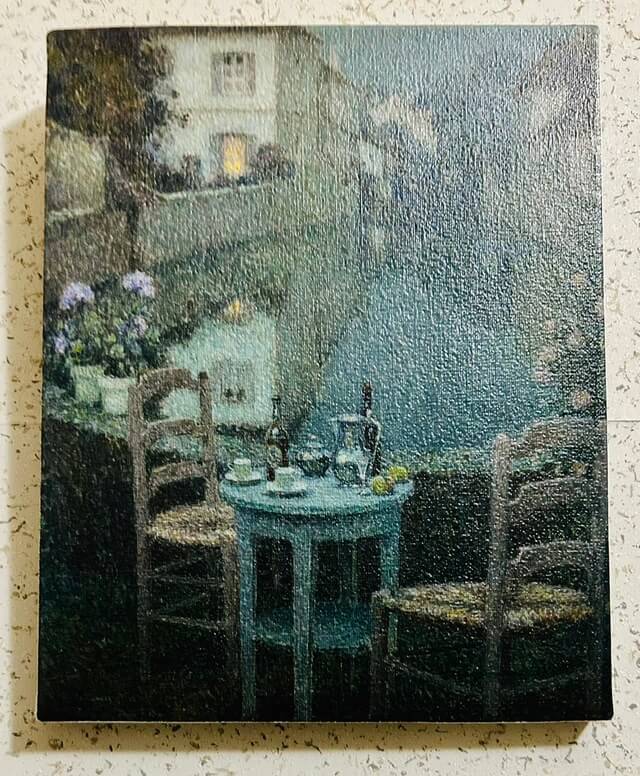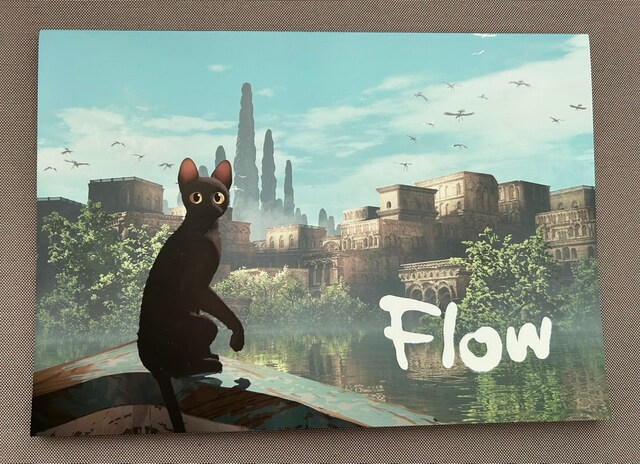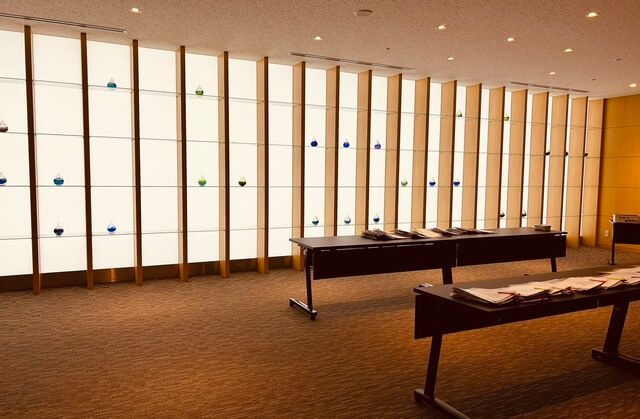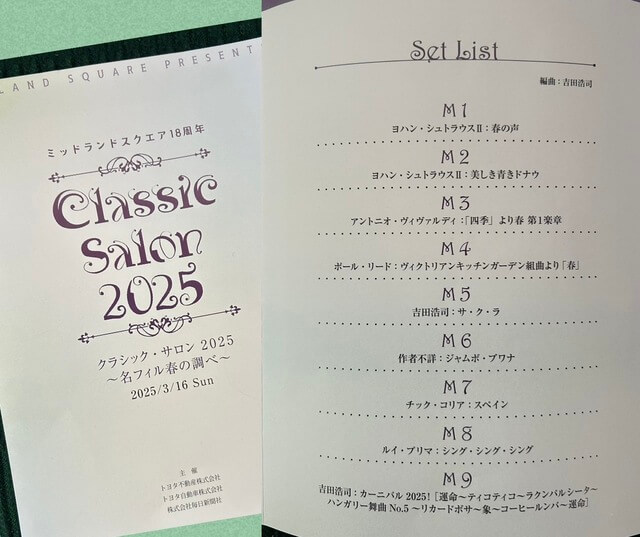元日夜は、恒例のウィーンフィルニューイヤーコンサート。
今年は、とにかく楽しかった。
そしてプログラムには、
異文化への理解、女性への敬意が感じられ、
新たな試み、伝統ある歴史の変革の年だったのでは。
カナダの指揮者
【ヤニック.ネゼ=セガン】
2022年、ウィーンフィルアメリカ公演の折、
ウクライナロシア戦争のため指揮者が来米できず、急遽、代役でウィーンフィルを救った、
明るくエンターティナーな資質の指揮者。
プログラムは例年と指向が違い、
インド、エジプト、黒人霊歌、アラビアンナイトにまつわるもの、
異文化の曲目が目新しかったです。
女性だけのオーケストラを作り、
1870年アメリカ公演を実現し、
1873年ウィーン万博でも指揮者として活躍した、
作曲家であり母でもある、
【ヨゼフィーネ.ヴァインリヒ】の
女性らしい甘く可愛らしい曲。
アフリカ系アメリカ人女性の
【フローレンス.プライス】
黒人霊歌やジャスのリズムと西欧を融合させた『レインボーワルツ』
これまた、ウィーンフィルが奏でると素敵で。。。
19世紀の欧州では、まだまだ弱い立場の女性。
その頃作られたシュトラウスの『女性の尊厳』ワルツ。
そして、
今年はウィーンフィル初来日から70周年。
指揮者が、【ヒンデミット】だったとは…。
コンマスは【ボスコフスキー】
なんだか、凄すぎる。
アンコールのラデツキー行進曲では、
指揮者が客席降りをして、会場が一体化し、
最後列のお客様は楽しかっただろうなぁ…と。
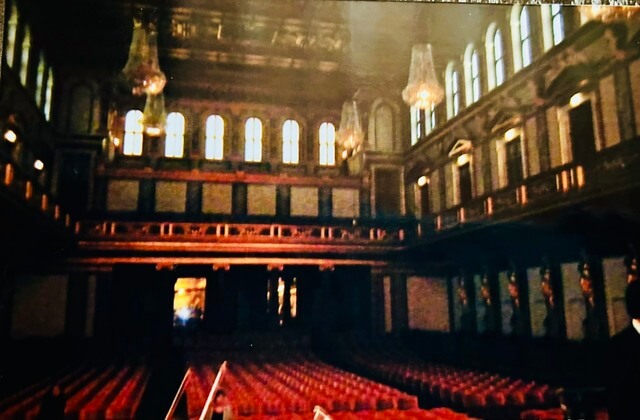
指揮者の恒例スピーチ
「それぞれの違いを受け入れれば、平和が訪れ、
kindnessが大切。
だって、same PLANETに居るのだから」
指揮者のお人柄が滲み出るニューイヤーコンサートでした。
楽しかったぁ!

来年はロシアの指揮者。
奇跡のような同じ地球に居るのだから、音楽を通して世界が穏やかになりますように。
今年は客席にバイオリニストの
【アンネ.ゾフィームター】を見つけ、
客席を見渡すのも楽しみのひとつです。

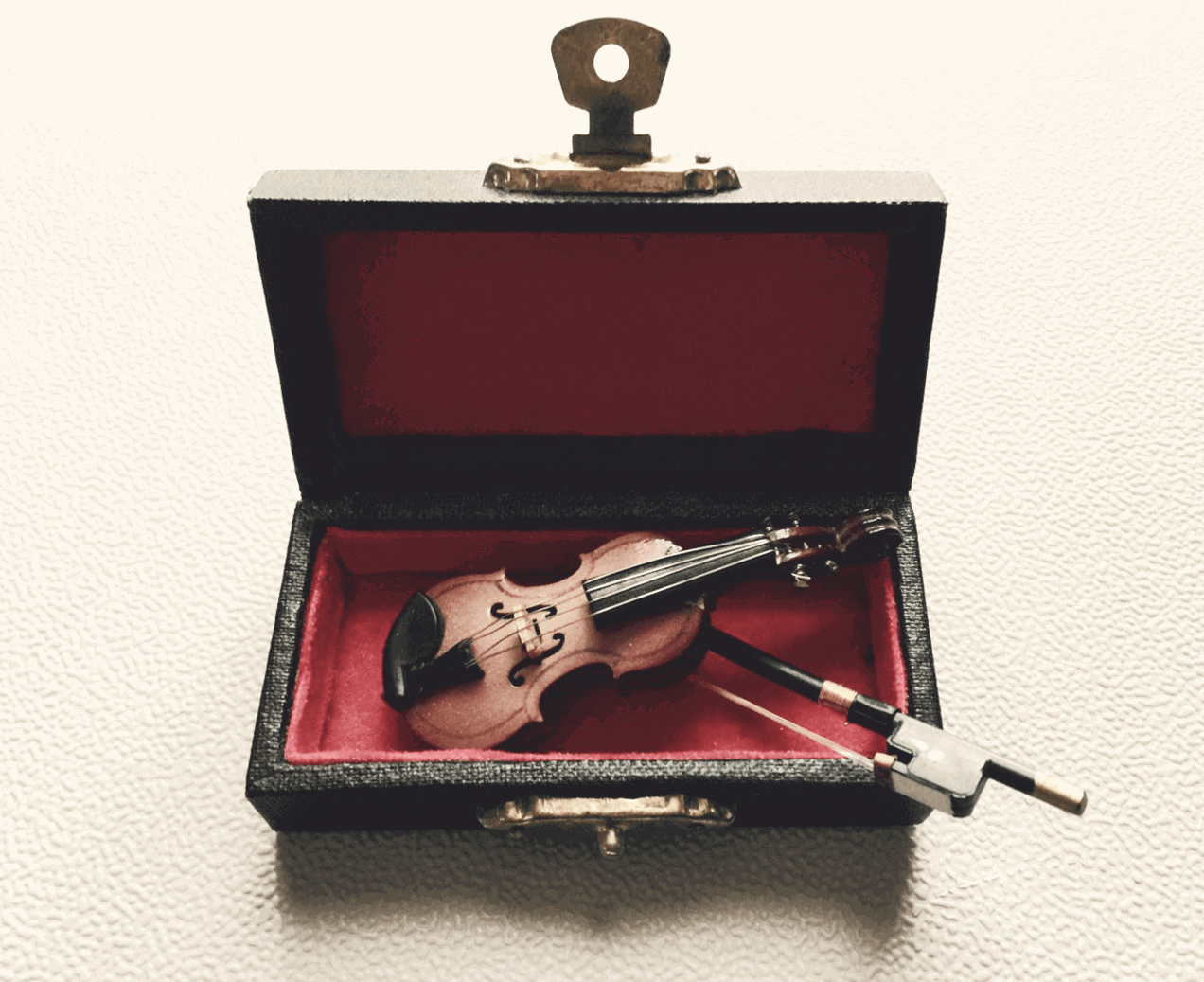








 2025新春、南座で初笑いさせていただきました。
2025新春、南座で初笑いさせていただきました。