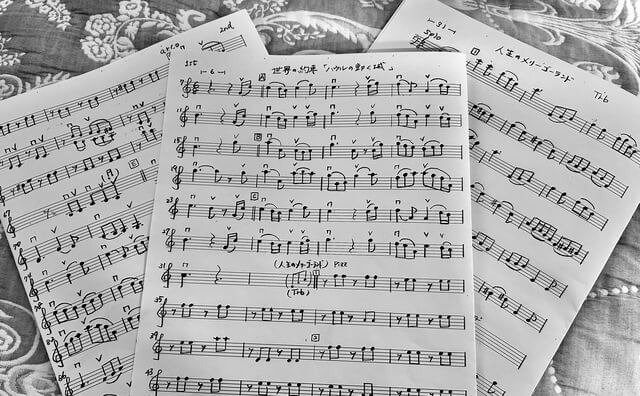2025. 1月8日.
京都南座での松竹新喜劇にお邪魔しました。
初めての南座。
お話は、
シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を元に、
時は大正、新喜劇らしく、面白可笑しく、客席降り、テンポ感もあり、
初笑いさせていただきました。

<↑撮影許可あり>
松竹新喜劇は、マンネリの笑いではなく、ちゃんと(?)面白い。
ベテランの曾我廼家文童さんもご出演で、
場を引き締めていらっしゃいました。
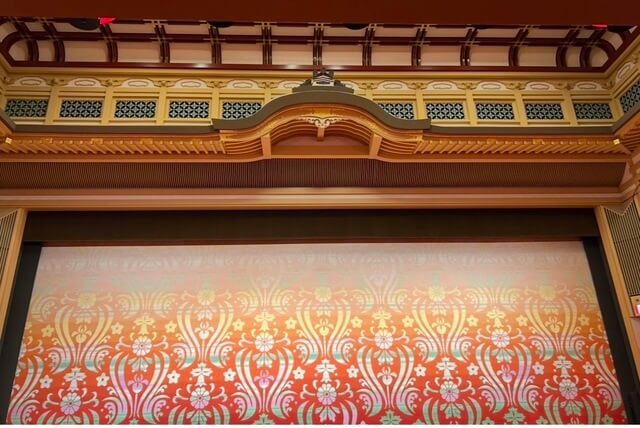
音楽でもメンデルスゾーンが、
『真夏の夜の夢』を作っており、
その中の『結婚行進曲』が、一番有名ですが、
個人的には序曲を弾くのが楽しかったです。
そして、
さすが京都。
一階桟敷席、上手側の席には、
花街らしく、舞妓さん芸妓さん方が、艶やかにたくさんの華を添えていらっしゃり、
私達観客も、目で楽しませていただき満足です。

一歩、外に出れば、
海外の観光客が非常に多く、
「う〜ん…古都が…」と思ってしまったりして…。

大学時代、
『四芸祭』というものがあり、
東京芸大、京都市立芸大、金沢美工大、そして愛知県芸大の国公立四大学で、毎年ホスト校が変わっての交流会がありました。
京都大会の折、
記憶では、この南座の裏あたりの小さな旅館に多勢で数日宿泊。
近所の銭湯を利用した際、
芸妓さんの名前が書いた籐籠がたくさんあり、
若干二十歳くらいの私は、
お姐さん方の私物から、
初めて日常の京都らしさを感じたものでした。
京都は観光客が多いだろうと、
今まで、あまり足を運びませんでしたが、
久々に祇園四条から烏丸まで気のむくまま散策し、
ちょうどお客が途切れていた鴨川沿いのレストランで、静かに外を眺め贅沢な時間。


森鴎外『高瀬舟』の舞台。
物流のために造られた運河『高瀬川』
立ち並ぶ現代の建築物に、
何か想像力が膨らむ…というのも難しいですが、
「そうそう、高瀬川、ここにあった!」と
若い頃も今も出会ったとき、なぜか嬉しかったです。

松竹新喜劇は、
来年お正月も、この南座公演が決定らしいです。
来年も初笑いをさせていただきたい。
そして皆さんにも、
この上質な「笑い」を知っていただきたい。


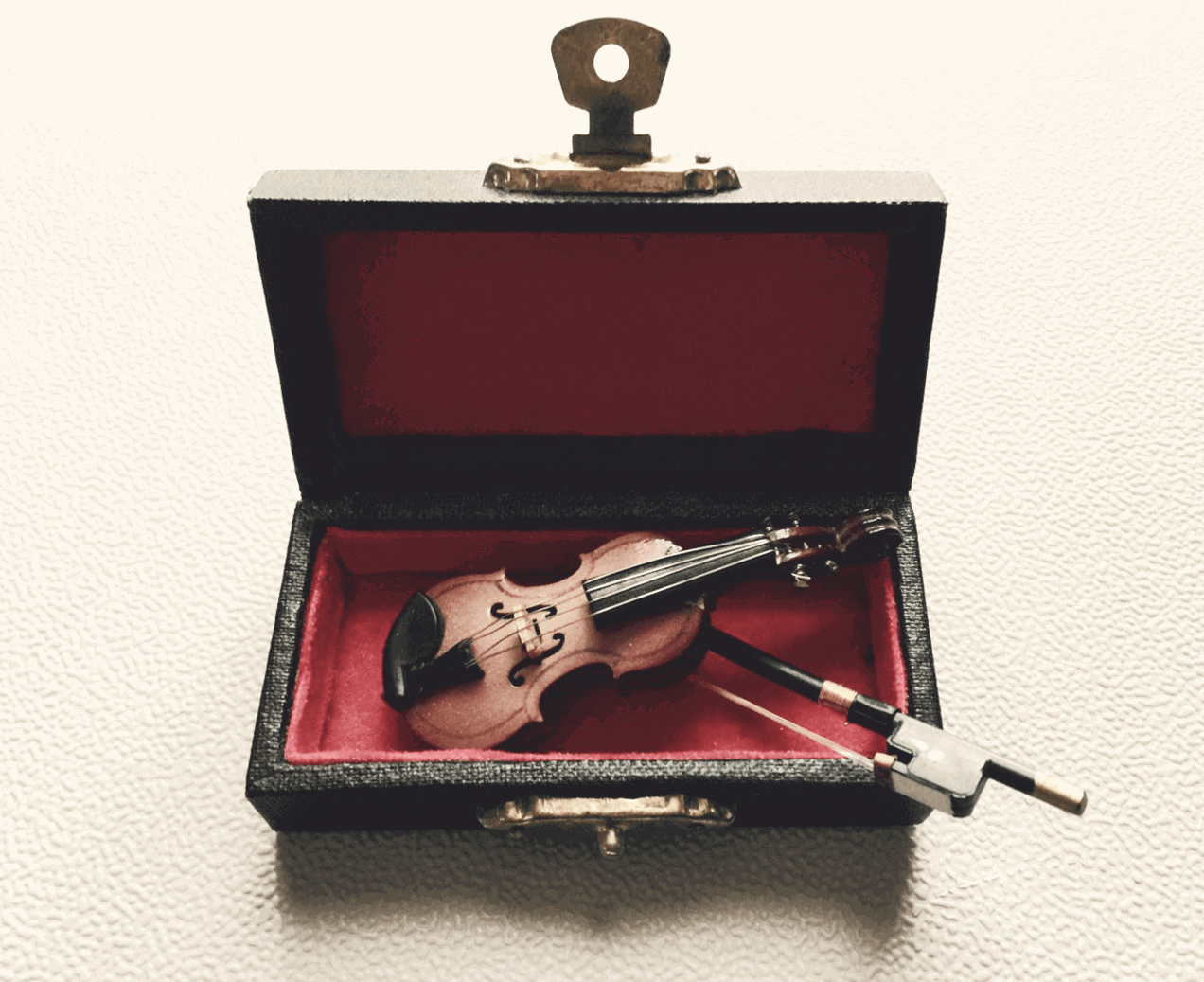



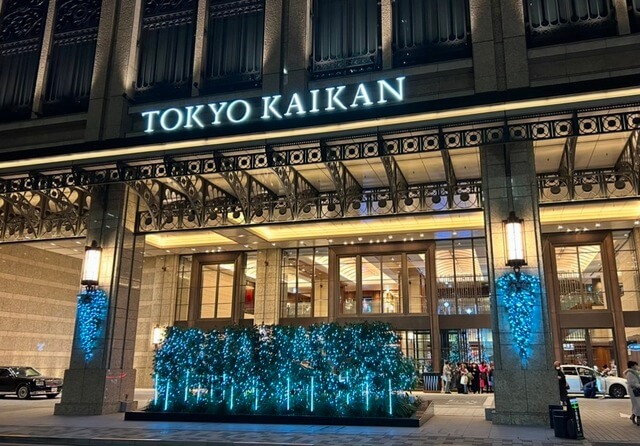




 2024.12/4、
2024.12/4、

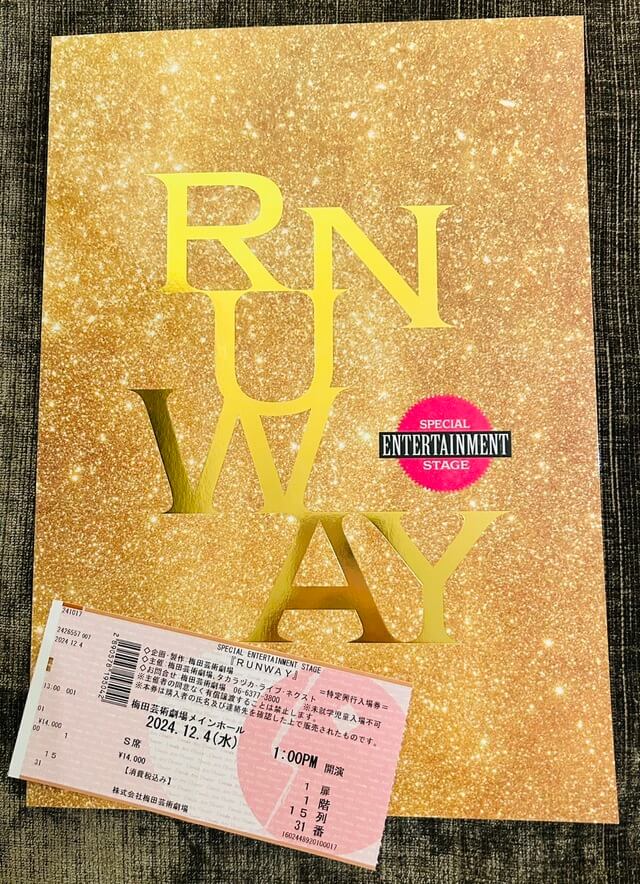






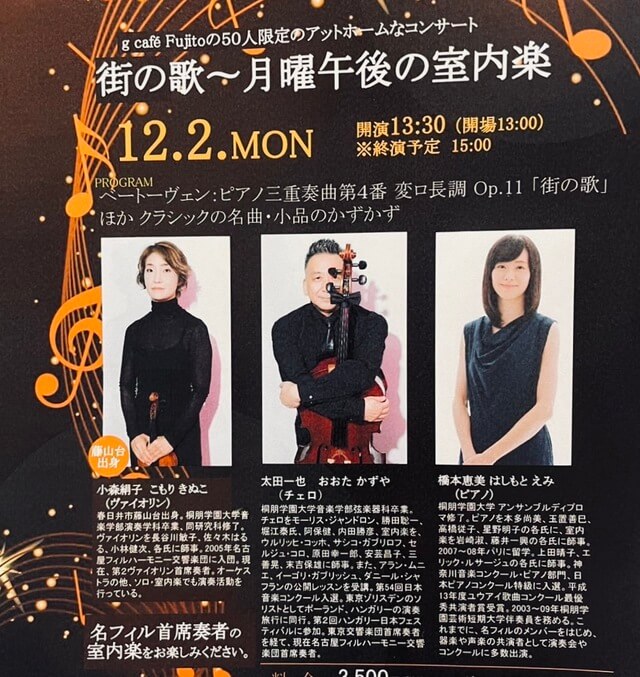

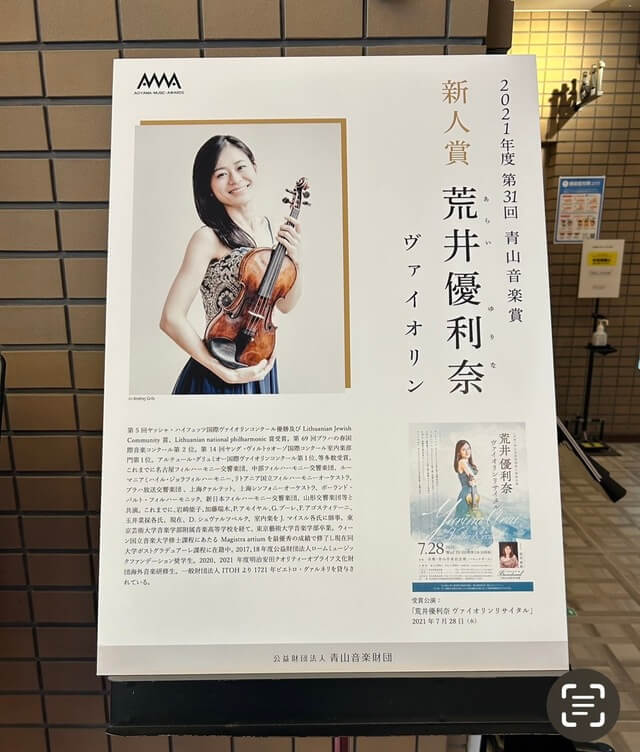
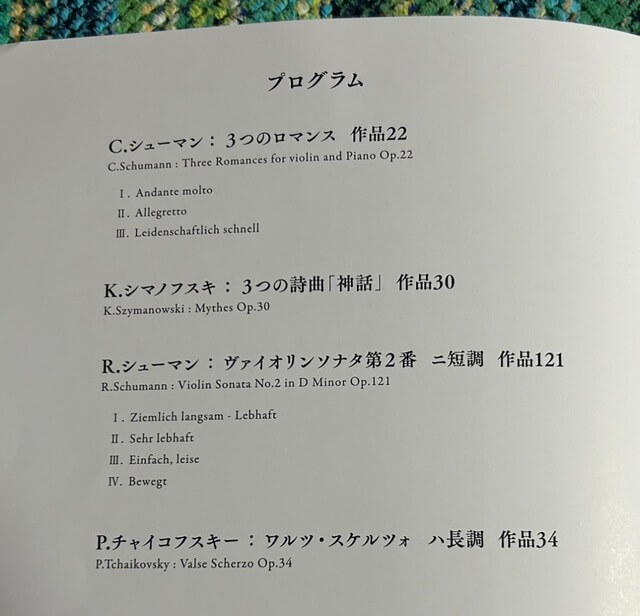





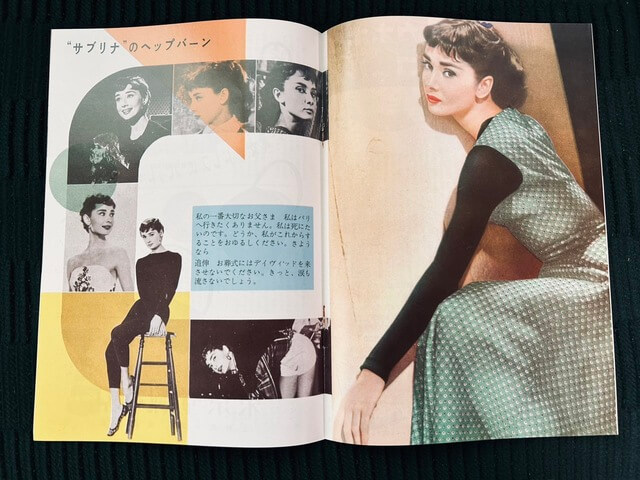

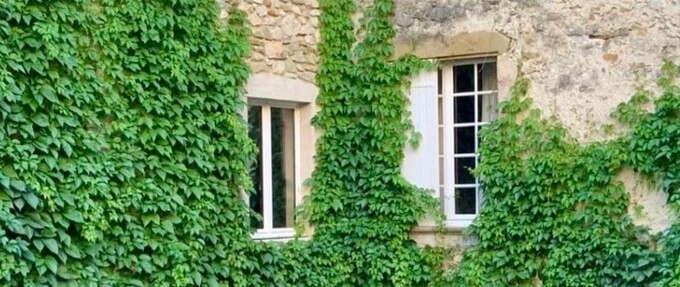
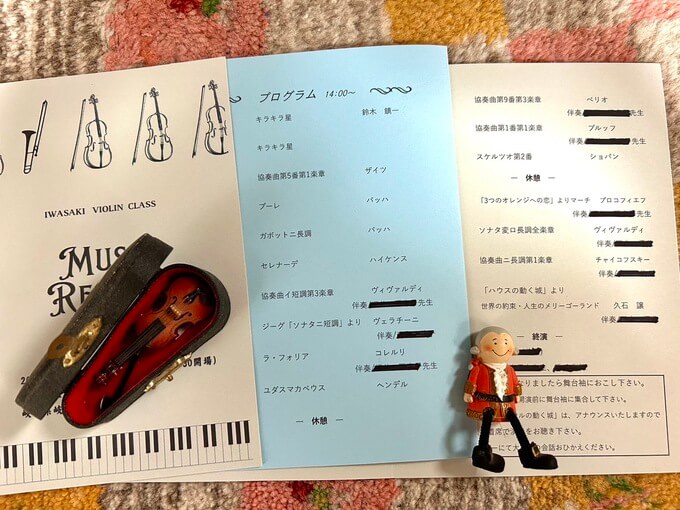
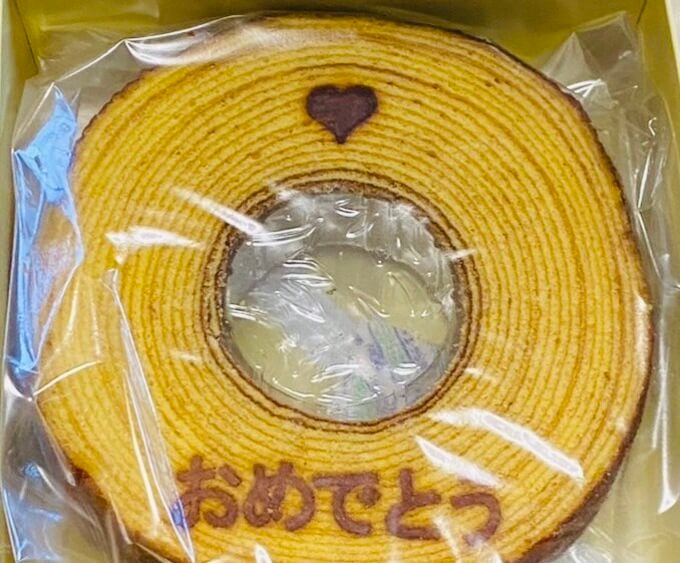

 2021年、
2021年、