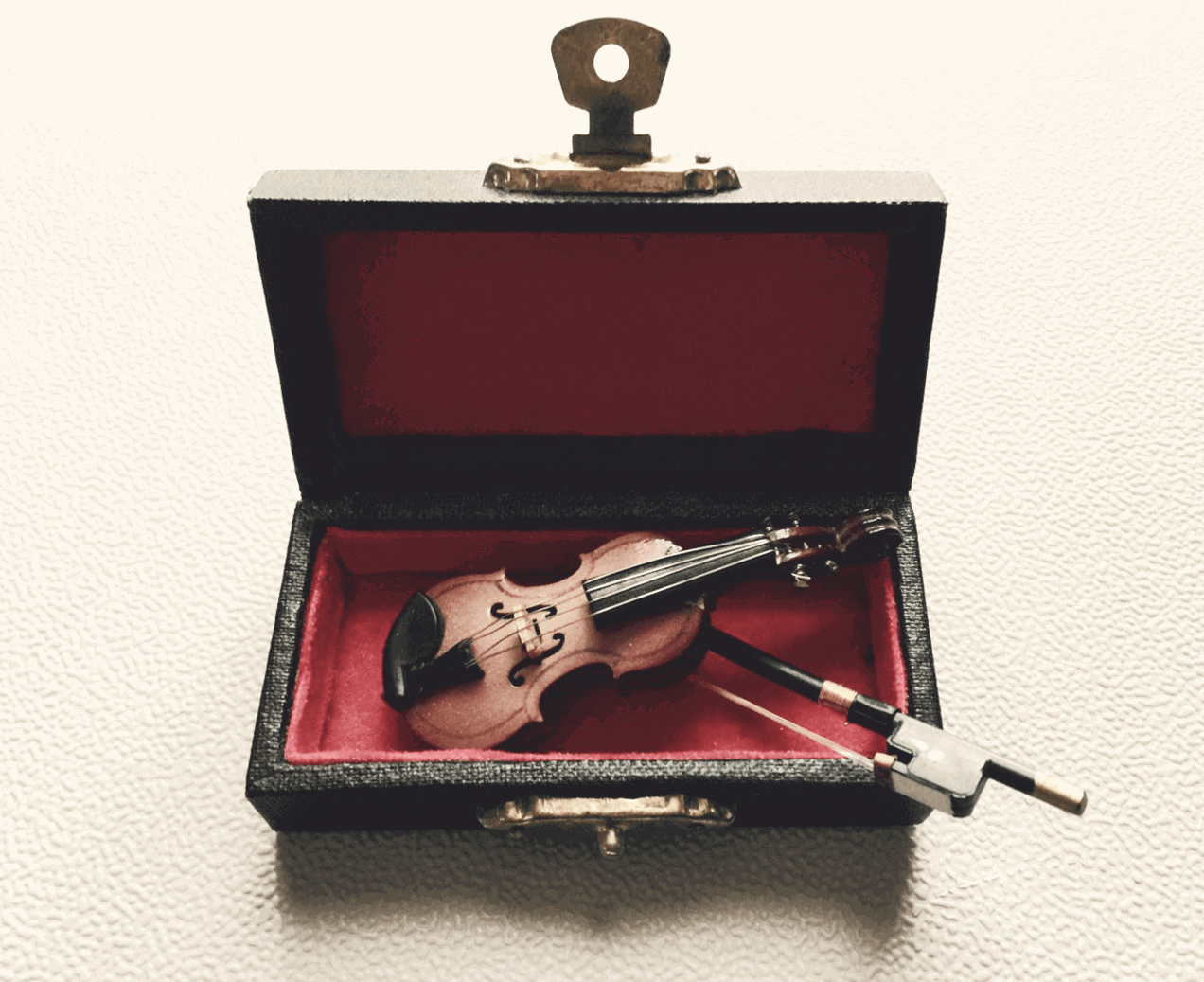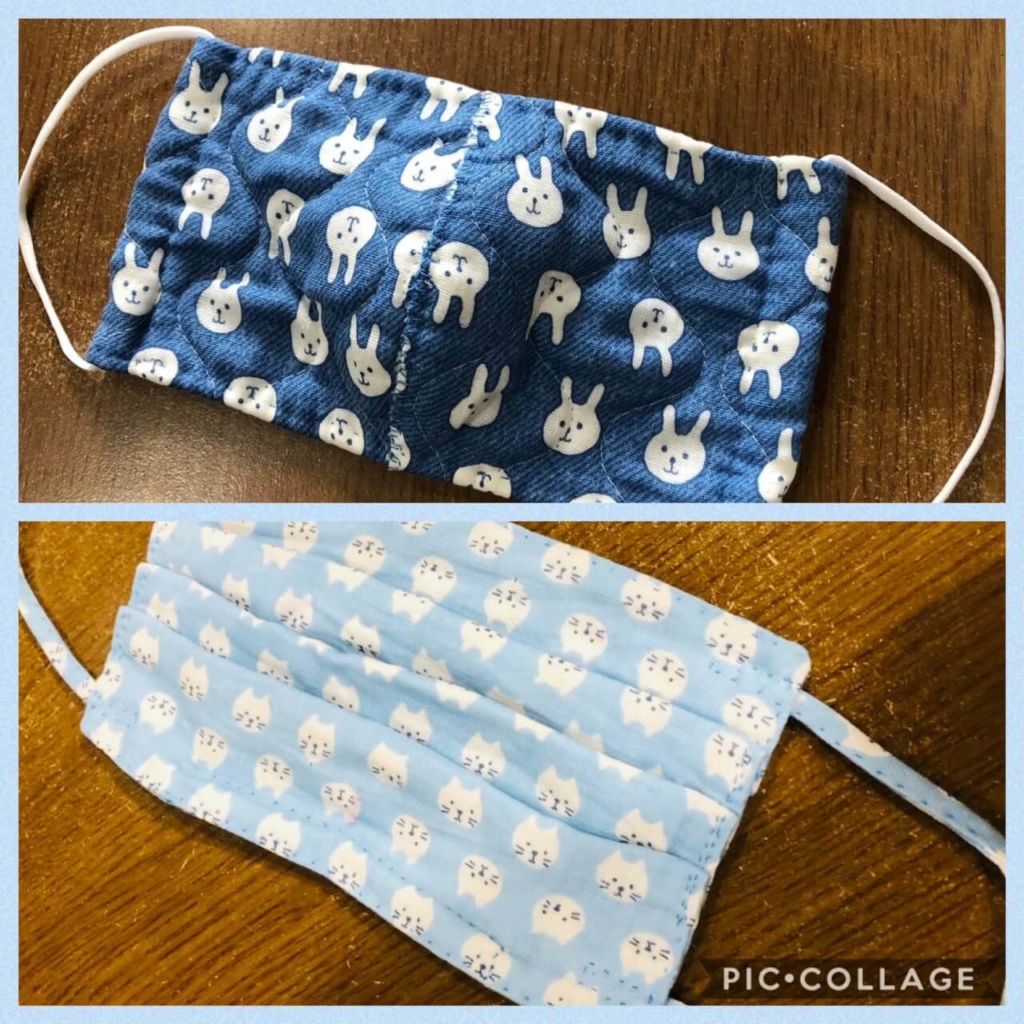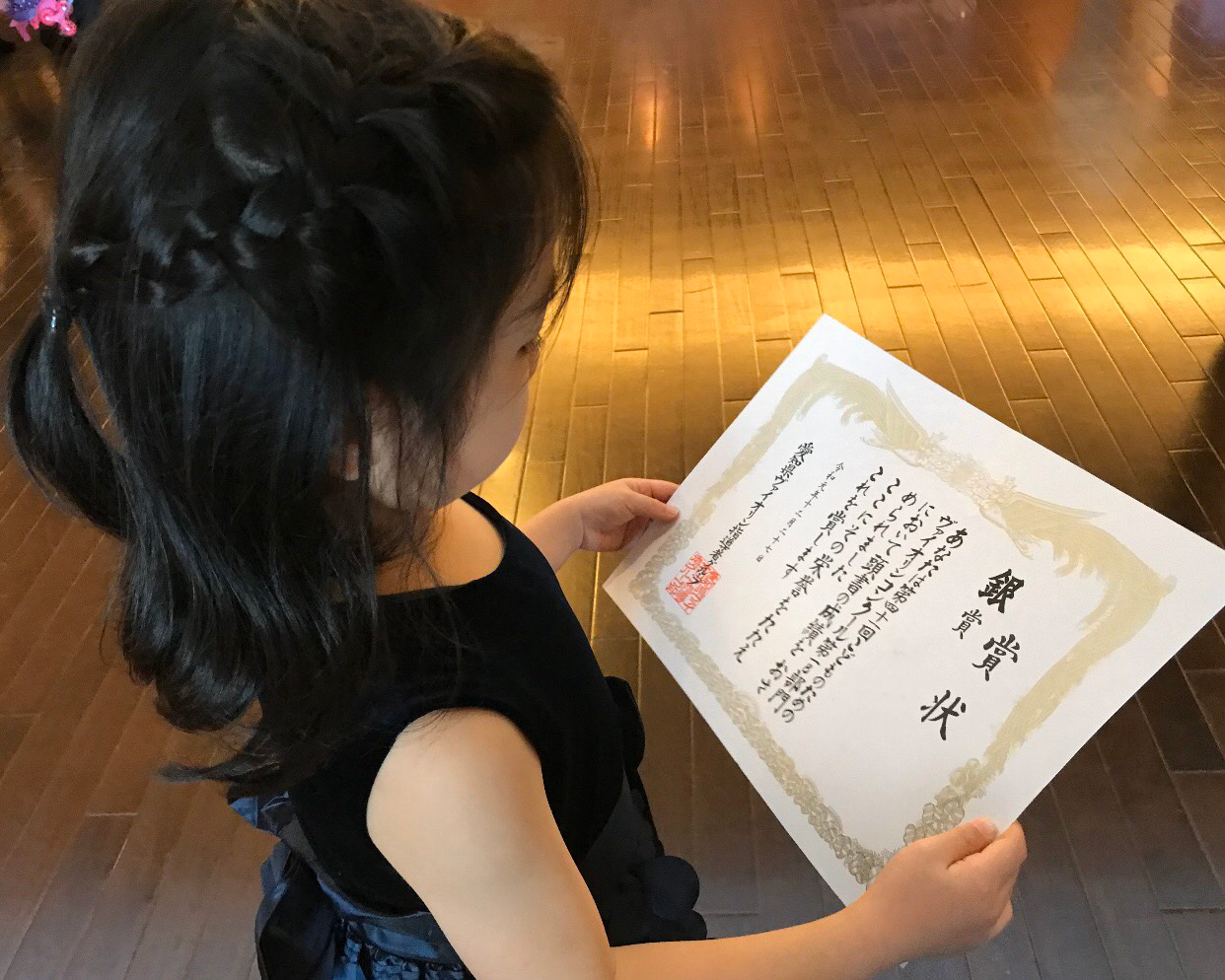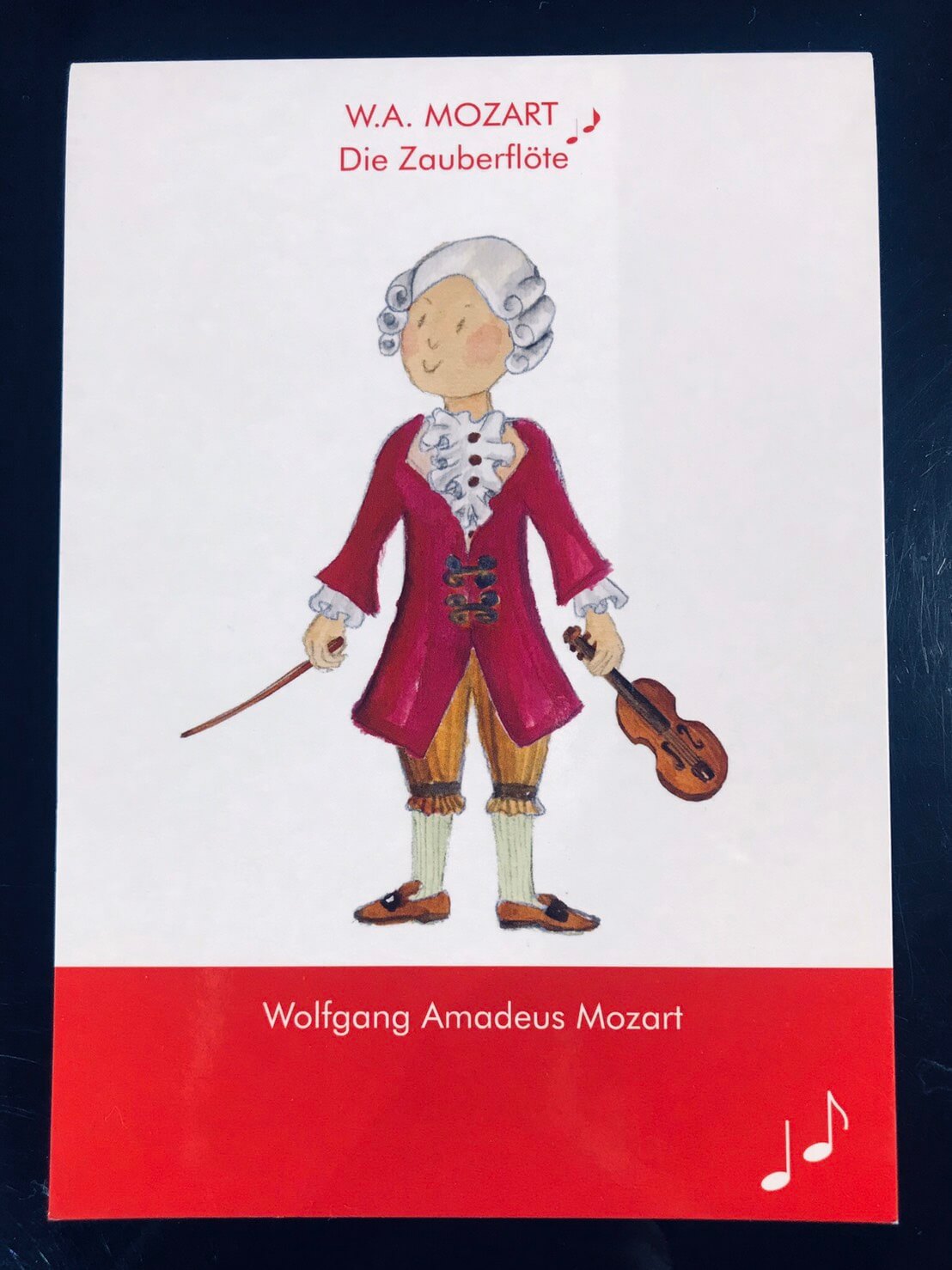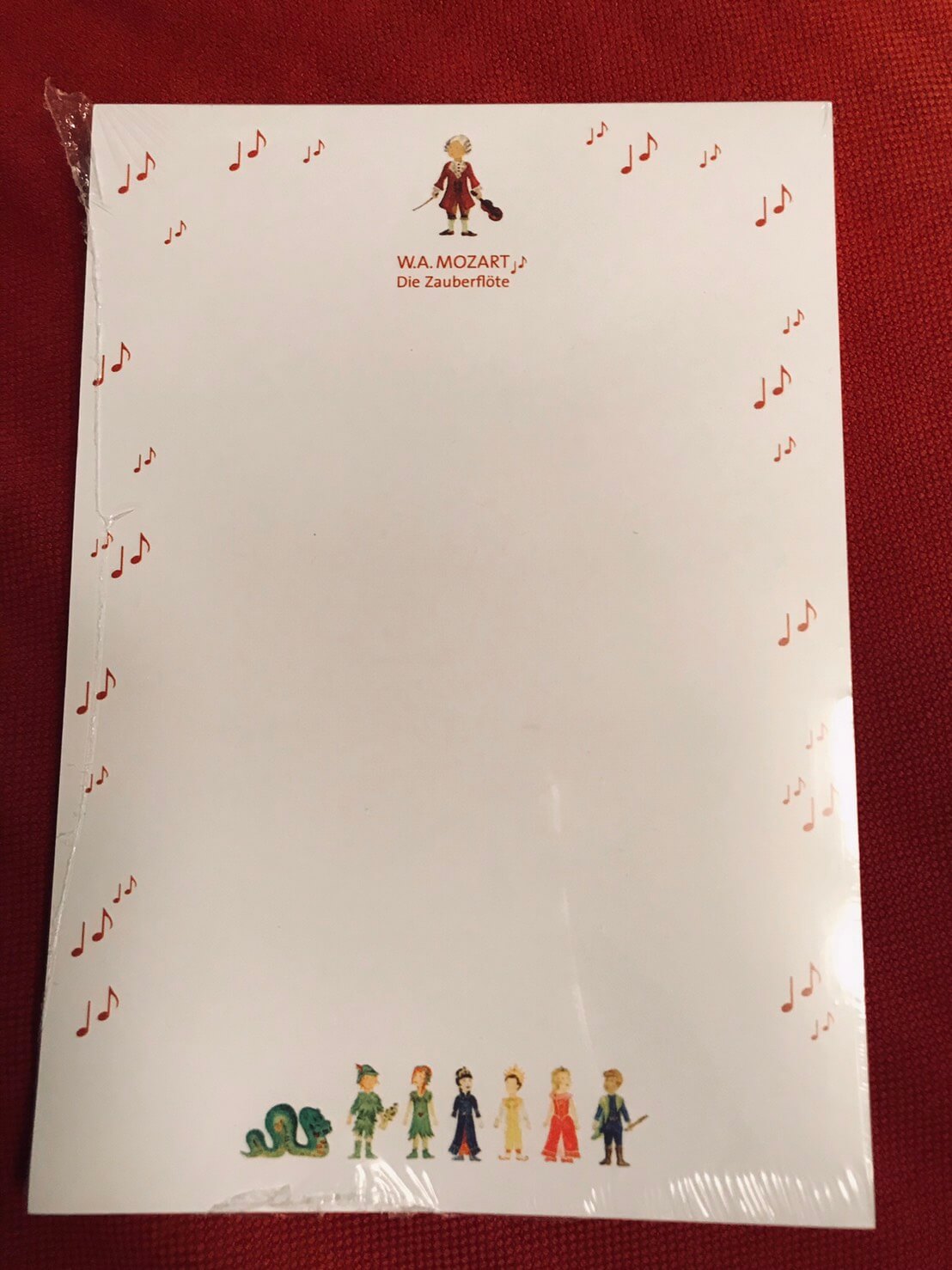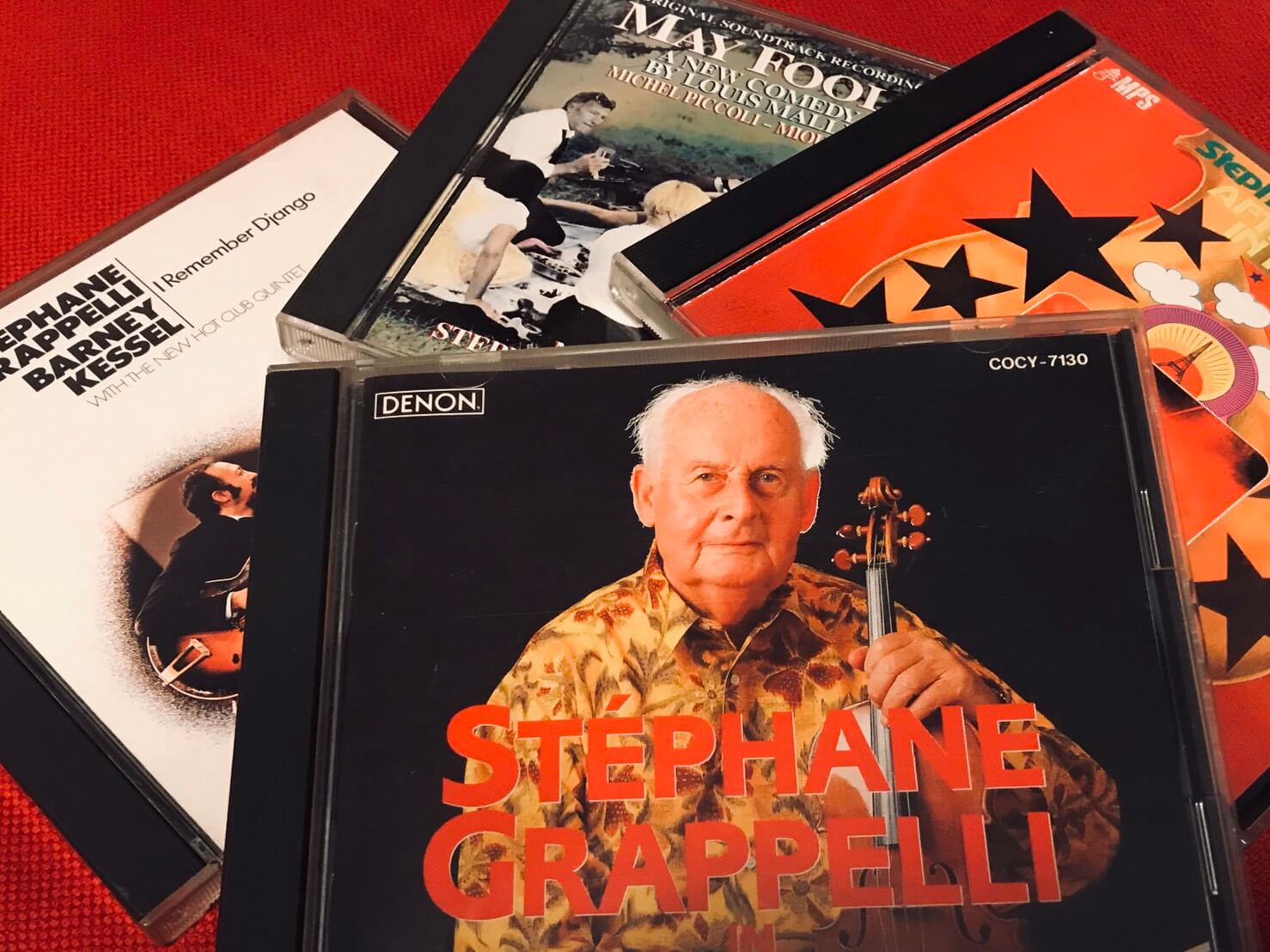少し前、ふとCMから流れてきた
「somethin’ stupid」の心地よさを感じ、
早速、この曲に浸りたくなりYouTube検索。
元々はフランク.シナトラと娘さんの仲睦まじい(シナトラはいろいろ黒い噂もありますが…)デュエットソングです。が
邦題「恋のひとこと」。
故大滝詠一と竹内まりやのハーモニーもとても素敵です。(こちらの方が良いかも)
間奏のストリングス(弦楽器)の高音のアレンジも、どこか遠い異国へ誘ってくれているようで、
昭和の時代のストリングスの使い方、好きです。
すごく古いですが、
昔、深夜に流れていた城達也のラジオ番組、
『ジェットストリーム』のテーマ曲、「Mister.lonely」もストリングスの音色に、一日の終わりの癒しを感じていました。…まだ、大学生でしたが(笑)

高校時代、爆発的に売れた、
『A long vacation』『ナイアガラ トライアングル』のアルバムで、大滝詠一、佐野元春などを知り、
(私達、音楽科のクラスでも、カセットテープが出回るほど)
大滝詠一のアンニュイだけど、上手くて甘い歌声に、どんな人だろう??と、
友人達と想像していました。
……今のようにすぐ検索できませんからね。
特に印象的だったのが、
私の記憶が確かかどうかわかりませんが、
海辺で、松坂慶子さんが、品良く美しく素敵なサマードレスでグラスと共にたたずむ、眼薬のCM。
BGMは、大滝詠一の「カナリア諸島にて」。

この曲も素敵なストリングスのアレンジが入り、このCMが流れるたびに、ブラウン管を観ていました。
弦楽器の典型的な特長を上手く取り入れているアレンジを聴くと、
なんだか、素直に「いいなぁ」って、
こんな複雑な時代だからか、感じます。
カナリア諸島…どこにあるの?と、
高校時代調べた記憶があります。
アフリカ大陸の横、スペイン領で欧州人の避暑地。
昭和の時代は夢のまた夢の異国。
平成になり、海外がとても近くなりましたが、
令和が始まり、今は、別の意味で遠いですね。