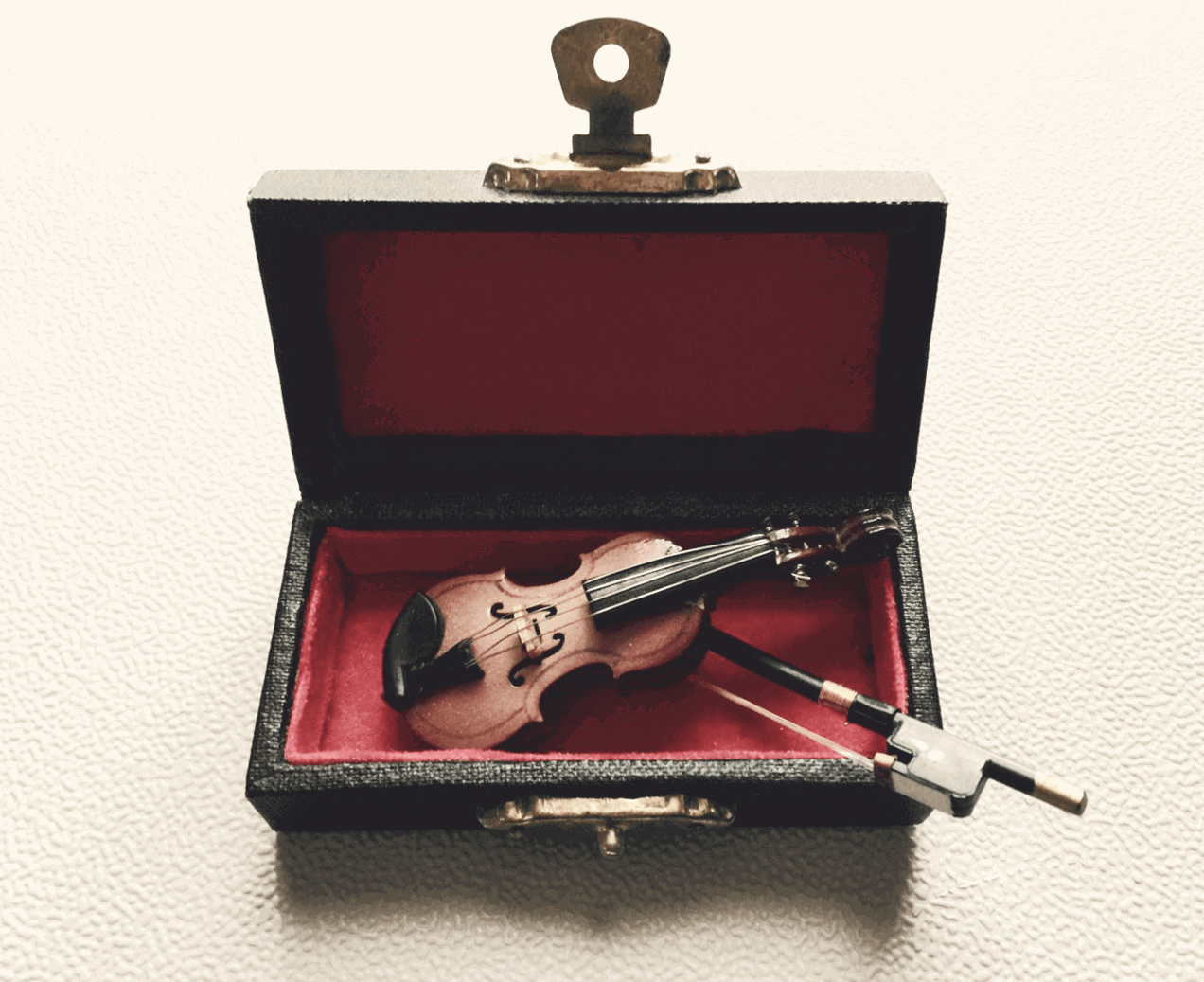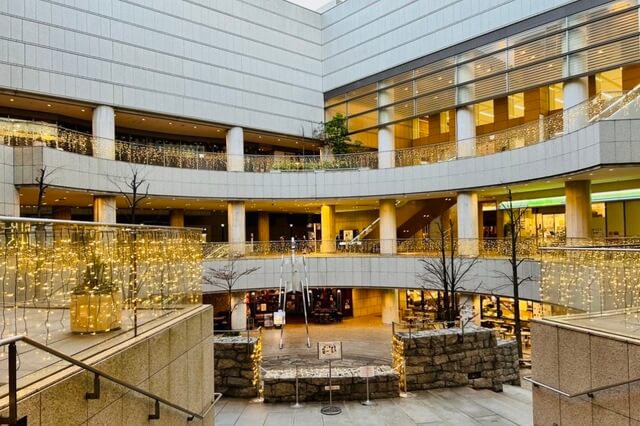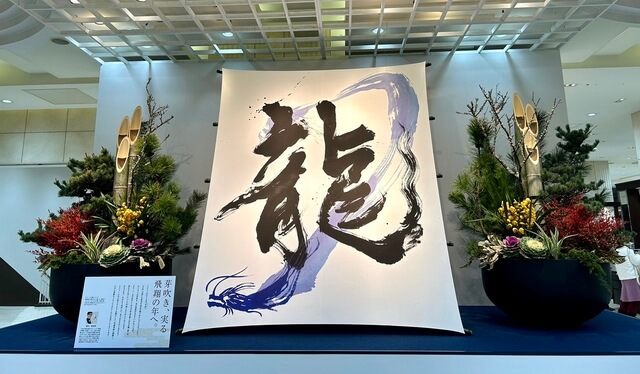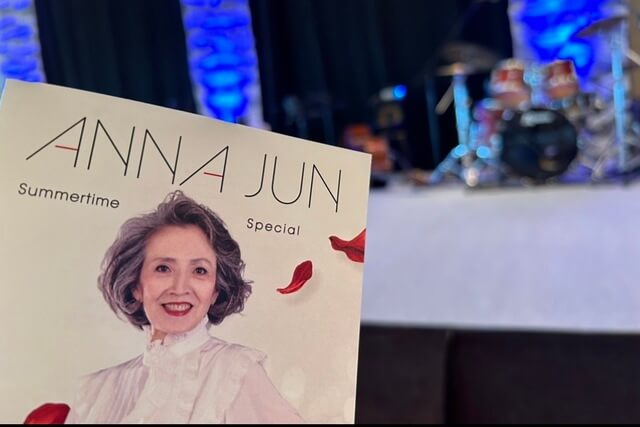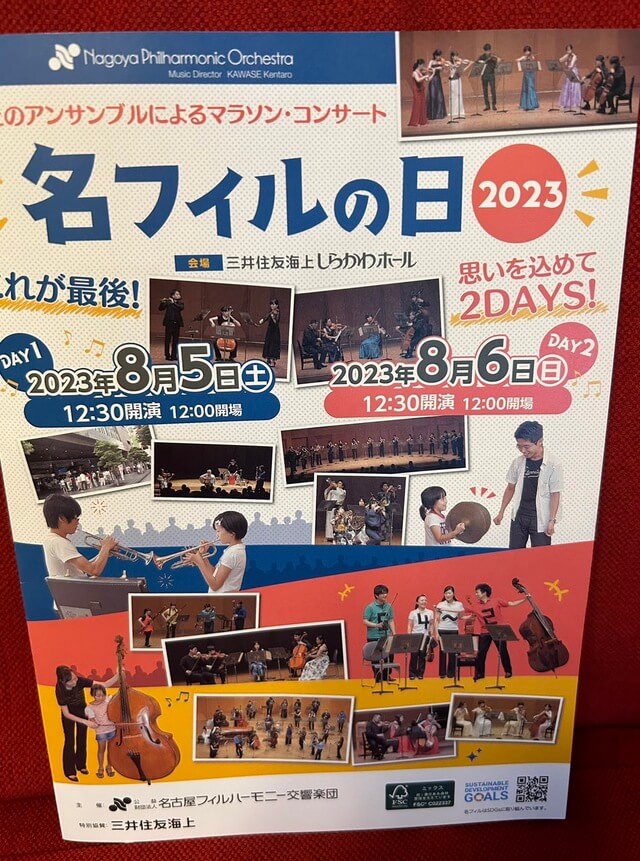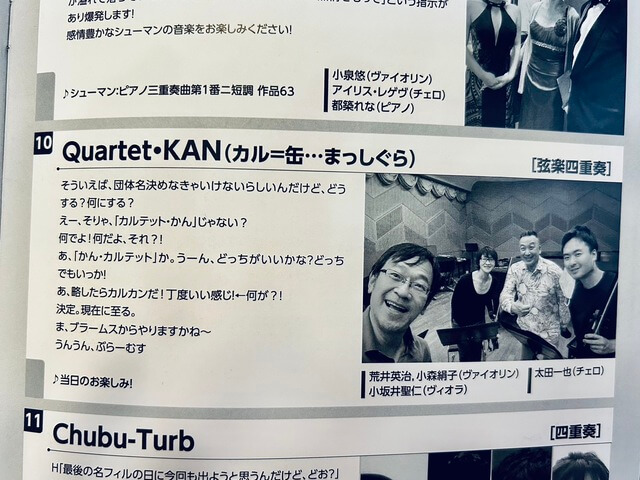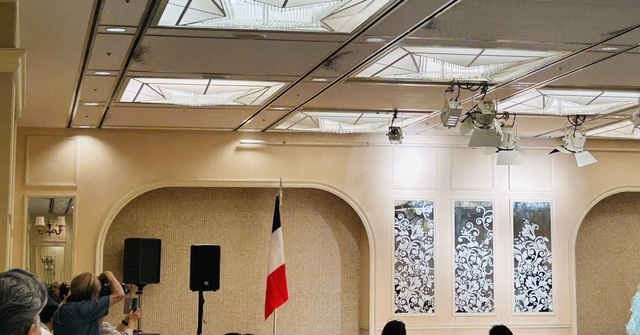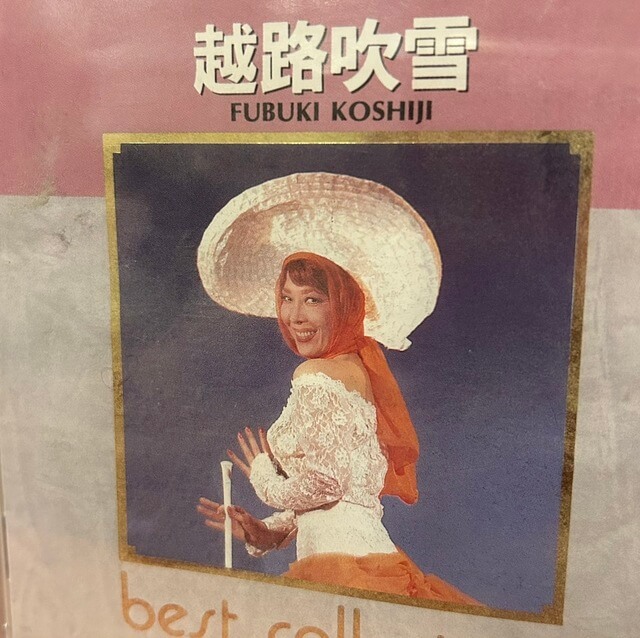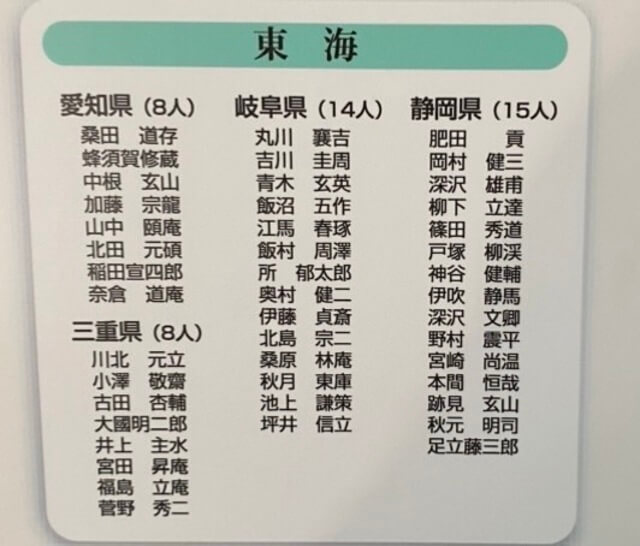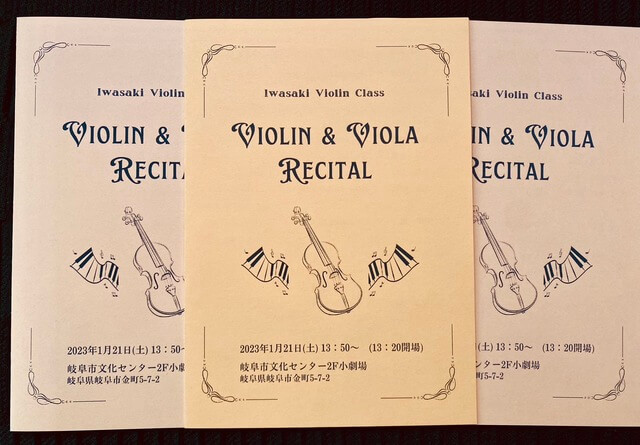昨年、
ドラえもんの映画の子供オーケストラ団員を募集しているので、
生徒さん(兄妹)とお友達4人でカルテットを組んで応募しました!と、
報告があり、
「合格するといいねぇ」
「ジャイアンの服でも着てアピールしたら」
なんて、話していたら、
あれよあれよとオーディションを通過していき、
ついに、
『ドラドラ♪シンフォニー楽団』30組のメンバーに選ばれました!と、
嬉しい報告がきました。
何度かテレビ朝日での練習があり、
葉加瀬太郎さん、芳根京子さんも参加して、

いよいよ、
2024.2月24日
東京大手町の日経ホールにて、
沢田完氏指揮「夢をかなえて」
葉加瀬太郎氏作曲指揮「君のポケット」のコンサートと、
ひと足早く、
「ドラえもん、のび太の地球交響曲」の試写会がありました。
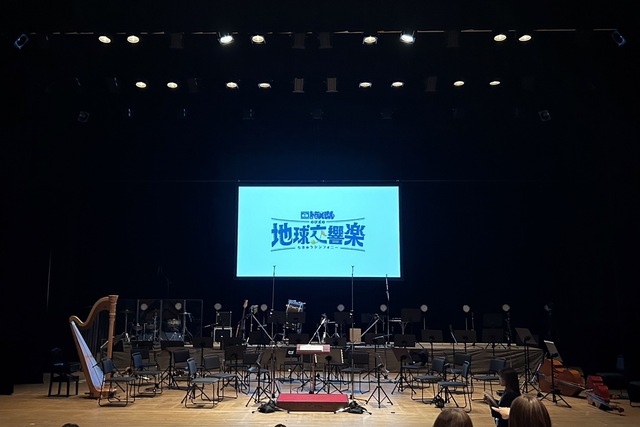
有り難くも、
私もお席をご用意いただき、
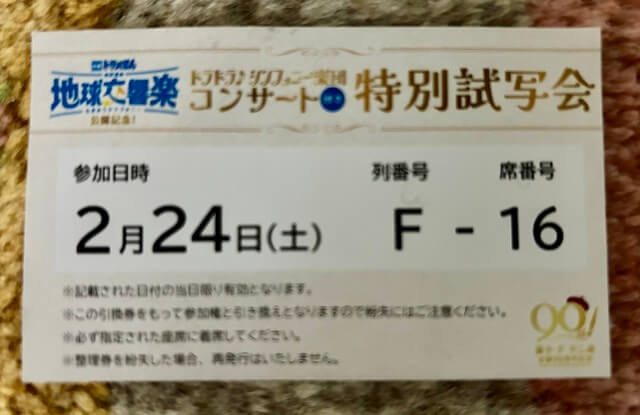
子供達のアンサンブル練習の成果に感動し、
葉加瀬太郎さん、芳根京子さん、芸人のかが屋さん、テレ朝アナウンサー坪井さん(久米宏さんの頃のニュースステーションでバイオリンを披露していたのを記憶しています)
もちろん、
モーツァルトヘアーのドラちゃん登場で、会場は盛り上がり、
客席の手拍子も熱かったです。
三味線等、いろいろな楽器のアンサンブルで、
小学生のこの時期に、同世代で違う楽器に触れ合うことができ、
合奏ができること。
しかも、曲はノリノリに楽しい🎶
ドラちゃんや葉加瀬さん、芳根さん、かが屋さんにもお会いでき、
映画のエンドロールにも名前が載り、
羨ましい限りです。
前日練習、
当日練習も時間が長く、
小学年には辛いかもしれませんが、
楽しいイベントで、
「我慢」「忍耐」「静かにお話を聞く」「同じ目標に向けみんなでひとつになる努力をする」
それだけでも、大きな成長のきっかけになる経験をしたと思います。
葉加瀬太郎さんの作曲した曲は
Fdur(へ長調)
これは、ドラちゃんのドとラ、藤子F不二雄先生のF(ファ)。
ファラドで構成されるへ長調の曲の
「きみのポケット」。
ちゃんと意味がありました。
ここ4ヶ月あまり、
私もドラえもんの曲が大好きになり

音楽は瞬間芸術ですから、
終わってしまえば消えてしまいますが、
子供達の心、親さんの心にも一生残る素敵な瞬間だったと思います。
もちろん私にも。
親さんの
「音楽を続けてきて、こんな素晴らしい機会と仲間をいただけたことが嬉しいです」と。
この言葉が私も何より嬉しいです。
音楽は素晴らしいと子供達に教えてくれた
ドラえもんとみんな!
♪♪♪ありがとう♪♪♪